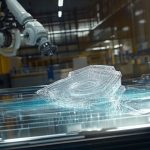(1)原油の種類や用途について
現代においてエネルギーの中核をなしているのが石油です。
石油は、燃料として使用されるほかにもさまざまな長岡石油などの石油製品の原材料となるものであり、身近に存在するあらゆるものに石油が使われています。
このため石油なしには現代の生活は成り立たないもので、そのような石油にもいくつかの種類があり、一般的にはガソリンや灯油が燃料は日常生活をしていく上で身近なものです。
これら石油は精製されたものであり、その原材料となるのが原油になります。
原油は、一般には精製されていない石油のことですが、採取された時の状態ではなく湧出または掘り出された時点では余分なガスや水分、また砂利などの異物が含まれておりこれをあらかた取り除いて輸送しやすくしたものです。
見た目には、黒くて粘り気のある液体ですが、さまざまな分子量の炭化水素の化合物が主成分となっています。
一方で、採掘される地域によって、その性質は異なり、含まれる物質として硫黄、酸素、窒素などを含んでいるもので、流通しているものの原油の組成は炭素83~87%、水素が11~14%、硫黄が5%以下でその他の元素は2%以下のものを指しているものです。
湧出または掘り出した時点で質が悪いと原油にするためにある程度の精製を行わなければならず、精製がほとんど不用な良質な産出地のものが広く使われていますが、資源は限りのあるものであり、経済を支える上で重要な資源であることなどから、近年はそれまで技術的または採算的に問題のあったものも使われるようになっており、それらはタイトオイルと呼ばれるものになります。
従来は液体が溜まっており、そこまで井戸を掘れば湧き出るものを使ってきましたが、タイトオイルでは湧き出るほどの圧力がない場所に水を送り込み圧力をかけて岩石の隙間などに含まれるものを取り出しているもので、取り出されたものは水が多く含まれるため精製する必要がありますが、そもそもの価格の高騰や将来に訪れるであろう資源枯渇を考慮して産出量が増加しているものです。
(2)原油の用途や採掘している国
原油が使われる用途は、身近な存在に燃料でガソリンや軽油はそれぞれエンジンを動かすために使われています。
また灯油は冬の暖房器具やボイラーなどの給湯器の燃料にも広く使われており、ガソリンスタンドで手軽に購入することができる燃料となっているものです。
このほかにもメタン、エタン、プロパン、ブタンといった天然ガスを抽出することができるため可燃性ガスの原材料ともなっています。
一方で、これらの燃料に適さず残ったものとして重油に分類され、こちらは船舶用のエンジンやボイラーなどに使われ、より粘度が高いものはアスファルトなどに使われているものです。
一方で石油は炭化水素の化合物であるため化学合成を行うことで、さまざまな合成樹脂を作ることができ、身近な製品に広く使われています。
将来的に見れば石油は燃料としてよりもこれら石油化学製品の原材料の重要性が高いと考えられており、燃料の消費量を減らして、石油化学製品のために資源を確保するといった動きも見られるほどです。
原油を主に採掘している国は、アメリカとサウジアラビア、ロシアですがそれぞれ全体の生産量から見れば、12%から14%程度になります。
5%前後の生産量を持っているのはイラン、イラク、カナダで、4%前後ではアラブ首長国連邦、中華人民共和国です。
ただ産出している地域だけで見れば中東が30%以上を占めており、この事からこの地域で紛争が起こった場合には価格が上昇する傾向にあり、特に日本にとっては1970年代に起こったオイルショックで知られます。
以前と比べて、この地域の問題は小さくなっていますが、それでも紛争等による問題での価格への影響は避けられません。
(3)日本では採掘もしているが、ほとんどを輸入に頼っている
また生産量はOPEC(石油輸出国機構)によって定められています。
生産量が多いほど供給が増えるので価格が下がる傾向にありますが、それぞれの国にとっては重要な外貨獲得資源であるため極端な減産や増産が行われるような合意が成立することはありません。
それと実際に合意が決定されてもペナルティがないため特に減産には従わないこともあります。
日本での需要はそのほとんどを輸入に頼っていますが、新潟県や秋田県、また北海道の勇払平野などで採掘が行われています。
採掘量は使用量に対してわずかに0.3%しかありません。
一方で輸入相手国としては中東が中心で、サウジアラビアやアラブ首長国連邦、カタール、イラン、クウェートなどから購入しており、全体の9割り程度を占めているものです。
過去のオイルショックの影響から石油備蓄が行われており、国家備蓄と民間備蓄を合わせて使用量に対して約197日分が備蓄されており、このような石油備蓄は経済力があり輸出入により経済が成り立っている国で行われており、現代では急激な減産が起こってもそれが価格にすぐに反映されるということは少なくなっています。
最終更新日 2025年5月20日 by rosseng