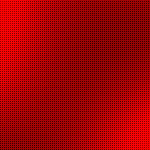年金基金やファンド運用において、最も大切なものは何でしょうか。
それは、運用成績という数字の先に存在する「信頼」ではないかと、私は考えています。
本記事では、30年以上にわたり金融業界に身を置き、現在は独立系アセットマネジメント会社の代表を務める私、佐々木信一の経験と視点から、この「信頼」の本質に迫ります。
大手運用会社での経験、そして独立系運用者としての現在の立場から見えてくる、数字だけでは語り尽くせない「人」との向き合い方。
それが、これからの資産運用において、どのような示唆を与えてくれるのか、一緒に考えていきましょう。
目次
信頼構築の核心:年金基金と運用の現場から
年金基金やファンド運用において、「信頼」は一朝一夕に築けるものではありません。
そこには、運用に携わる者の確固たる責任感と、透明性の高い情報開示、そして顧客との真摯な対話が不可欠です。
年金基金に求められる運用責任とは
年金基金は、多くの加入者の老後の生活を支えるという、極めて重い社会的責任を負っています。
その運用責任の根幹にあるのは、加入者の利益を最大限に追求する「受託者責任」です。
具体的には、以下のような点が求められます。
- 忠実義務: 加入者の利益のみを最優先に考え行動すること。
- 善管注意義務: 善良な管理者の注意をもって、専門家としての知識と経験を活かし、適切に業務を行うこと。
- 安全かつ効率的な運用: 託された資金を安全性を確保しつつ、効率的に運用すること。
- 情報開示義務: 運用状況や財務状況について、加入者や受給者に対して分かりやすく、適切に情報開示を行うこと。
これらの責任を全うすることが、年金基金に対する信頼の第一歩と言えるでしょう。
ファンド運用の「透明性」と「説明責任」
ファンド運用においても、「透明性」と「説明責任」は信頼の礎です。
投資家が安心して資金を託すためには、ファンドの運用方針やリスク、コストなどが明確に開示されている必要があります。
透明性とは、具体的には運用プロセスや投資判断の基準、どのような銘柄に投資しているのかといったポートフォリオの内容、そして手数料体系などを、投資家が容易に理解できるように示すことです。
そして、説明責任とは、運用成果について、特に期待したリターンが得られなかった場合に、その理由や今後の対応策などを、投資家に対して誠実に、かつ具体的に説明する責任を指します。
これらが十分に果たされて初めて、投資家は納得感を持ってファンドと向き合うことができるのです。
顧客との長期的関係を築くための要件
顧客との信頼関係は、一度築けば終わりというものではありません。
むしろ、時間をかけて育んでいくものです。
そのためには、以下のような取り組みが重要になります。
- 継続的な情報提供: 運用状況の報告はもちろん、市場環境の変化や今後の見通しなどを定期的に分かりやすく伝える。
- 双方向のコミュニケーション: 顧客からの質問や疑問に丁寧に答え、意見や要望に耳を傾ける姿勢を持つ。
- 顧客理解の深化: 顧客のライフプランやリスク許容度を把握し、一人ひとりに合った提案やアドバイスを心がける。
こうした地道なコミュニケーションの積み重ねが、顧客との長期的な信頼関係を強固なものにしていくのです。
リーマン・ショック以降に変化した信頼の形
2008年のリーマン・ショックは、金融業界全体に対する信頼を大きく揺るがす出来事でした。
リスク管理の甘さや、複雑で理解しにくい金融商品の販売などが問題視され、多くの投資家が損失を被りました。
この経験は、私たち金融に携わる者にとって、大きな教訓となりました。
「短期的な利益を追求するあまり、顧客の利益やリスクへの配慮が疎かになっていなかったか。」
「専門家として、分かりやすい情報提供と十分な説明責任を果たせていただろうか。」
こうした自省のもと、金融業界では透明性の向上や顧客本位の業務運営への意識が、以前にも増して強く求められるようになりました。
信頼の形は、より「顧客との対話」を重視し、「長期的な視点」に立ったものへと変化してきていると言えるでしょう。
独立系ファンドマネージャーという選択
私自身、長年大手アセットマネジメント会社に籍を置いていましたが、リーマン・ショックを一つの転機とし、独立の道を選びました。
そこには、より顧客に近い立場で、自らの信念に基づいた運用を追求したいという強い思いがありました。
金融業界においては、私のように既存の金融機関のあり方に疑問を感じ、顧客とのより良い関係性を求めて独立する動きは他にも見られます。
例えば、日興証券でのご経験から販売サイドに偏った金融商品や顧客との短期的な関係性に課題を感じ、2006年に独立してエピック・グループを設立された長田雄次氏も、顧客との長期的な信頼関係構築を重視し、ファンドの設立・運営支援を中心に事業を展開されています。
こうした動きは、業界全体にとって顧客本位のサービスを考える上で示唆に富むものです。
大手から独立に至る意思決定とその背景
大手組織に所属することの安定性やブランド力は、確かに大きなものです。
しかし、組織が大きくなればなるほど、意思決定のプロセスが複雑になったり、個人の裁量が制限されたりする側面も否定できません。
リーマン・ショック後の市場の混乱と、その後の金融業界の変革を目の当たりにする中で、「このまま大手にいても、守ることしか考えられなくなるのではないか」という危機感が募りました。
もっと機動的に、そして顧客一人ひとりの顔が見える距離で、真に価値のある運用サービスを提供したい。
その思いが、独立という決断を後押ししました。
地方銀行との連携と地方経済への貢献
独立後、私が注力したことの一つが、地方銀行との連携です。
地方には、独自の技術や魅力的なビジネスモデルを持ちながらも、資金調達や経営ノウハウの面で課題を抱える企業が少なくありません。
地方銀行と連携し、そうした企業を支援するファンドを設立・運営することは、地域経済の活性化に繋がり、ひいては日本経済全体の底上げにも貢献できると考えました。
例えば、以下のような取り組みが考えられます。
- 地域密着型ファンドの組成: 地元企業の成長資金や事業承継を支援。
- 経営サポート: 投資先企業に対し、財務戦略だけでなく、販路拡大や人材育成などの経営支援も行う。
こうした活動は、単にリターンを追求するだけでなく、社会的な意義を実感できるものであり、大きなやりがいを感じています。
ESG投資にフォーカスした独自戦略の構築
現在、私が運営するファンドでは、ESG投資を軸とした戦略を採っています。
ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の頭文字を取ったもので、これらの要素を重視する企業は、長期的に持続的な成長が期待できるという考え方です。
なぜESG投資なのか?
それは、短期的な業績だけでなく、企業が社会や環境とどのように向き合い、持続可能な成長を目指しているかという点が、これからの時代においてますます重要になると確信しているからです。
具体的な投資プロセスにおいては、以下のような点を重視しています。
- 環境への配慮: 気候変動対策、再生可能エネルギーの利用、廃棄物削減など。
- 社会との共生: 従業員の働きがい、人権尊重、地域社会への貢献など。
- 健全な企業統治: 取締役会の多様性、情報開示の透明性、法令遵守など。
これらの要素を丹念に分析し、真に社会から必要とされ、長期的に成長し続ける企業を選び出すこと。
それが、私の目指す運用スタイルです。
「守る」から「創る」へ:運用者の意識改革
かつての運用業界には、どちらかというと「市場の平均点を取る」「大きな失敗をしない」といった「守り」の姿勢が強かった側面があるかもしれません。
しかし、これからの時代に求められるのは、変化を恐れず、新たな価値を「創り出す」運用ではないでしょうか。
それは、ESG投資のような新しい投資手法への挑戦であったり、地方創生のような社会課題の解決に貢献する投資であったりするかもしれません。
運用者自身が、社会の変化を敏感に捉え、自らの役割を再定義し、主体的に行動していく。
そうした意識改革こそが、運用業界全体の信頼を高め、未来を切り拓く力になると信じています。
数字の向こう側を見る:佐々木流のリサーチ哲学
ファンドマネージャーの仕事は、日々膨大な情報と向き合い、投資判断を下すことです。
しかし、私は「机の上の数字だけじゃ、伝わらない」という信念を持っています。
企業の本質的な価値を見抜くためには、数字の裏にある「人」や「現場」に触れることが不可欠だと考えています。
徹底した現地取材と対話重視の姿勢
私がリサーチにおいて最も大切にしているのは、実際に企業を訪問し、経営者や従業員の方々と直接対話することです。
いわゆる「現地現物」の精神です。
企業のウェブサイトや決算資料から得られる情報は、もちろん重要です。
しかし、それだけでは見えてこないものがたくさんあります。
- 経営者の情熱やビジョン
- 従業員の士気や職場の雰囲気
- 製品やサービスが生まれる現場の熱気
これらは、実際に足を運び、五感で感じ取って初めて理解できるものです。
経営者や担当者との対話から得る“生きた情報”
経営者や担当者との対話は、私にとって最も貴重な情報源の一つです。
何時間でも話し込み、彼らが何を目指し、何を課題と感じ、どのような未来を描いているのかを深く掘り下げます。
そこから得られるのは、単なるファクト(事実)ではなく、彼らの「想い」や「哲学」といった、いわば“生きた情報”です。
例えば、ある企業の経営者が語る「自社の技術が社会のこの課題を解決できる」という熱意や、現場の担当者が語る「製品改善のための日々の試行錯誤」。
こうした言葉の端々から、その企業の真の強みや将来性、あるいは潜在的なリスクが見えてくることがあります。
「机上の数字」では見抜けない企業の本質
財務諸表に現れる数字は、企業の過去の実績を示すものです。
しかし、私たちが投資するのは、企業の「未来」です。
その未来を予測するためには、数字だけでは不十分です。
なぜ、その企業は成長し続けることができるのか?
なぜ、その企業は競合他社よりも優れているのか?
なぜ、その企業は困難な状況を乗り越えることができるのか?
これらの問いに対する答えは、多くの場合、その企業の持つ独自の文化や、従業員のエンゲージメント、経営者のリーダーシップといった、数値化しにくい「定性的な要素」の中に隠されています。
これらを見抜くためには、やはり現場に足を運び、人と対話し、自らの目で確かめるしかないのです。
執筆と語り:金融のリアルを伝えるもう一つの道
私はファンドマネージャーとしての業務の傍ら、専門誌や業界紙などでコラムを執筆する機会をいただいています。
これは、私にとって金融のリアルな姿や、運用に込める想いを伝える、もう一つの大切な道です。
業界紙・専門誌でのコラム執筆の意義
金融の世界は、専門用語が多く、一般の方には少し縁遠いものに感じられるかもしれません。
しかし、年金や投資は、私たちの生活と密接に関わっています。
だからこそ、金融の専門家が、分かりやすい言葉で、その仕組みや現状、そして未来について語ることには大きな意義があると考えています。
私のコラムが、少しでも多くの方にとって、金融や投資を身近に感じ、考えるきっかけになればと願っています。
また、同業者に向けては、日々の運用業務の中で感じた課題や、新しい視点などを共有することで、業界全体の発展に微力ながら貢献できればと考えています。
読者に誠実であるための文体と語り口
文章を書く上で常に心がけているのは、「読者への誠実さ」です。
専門的な内容であっても、決して専門用語をひけらかすのではなく、誰にでも理解できるように平易な言葉で伝える。
そして、自らの意見や分析には、必ず根拠を示し、客観性を保つ。
時には、金融の世界の厳しい現実や、私自身の失敗談なども包み隠さずお伝えすることもあります。
それは、読者に対して常に正直でありたい、という思いからです。
一見堅いと評されることもある私の文章ですが、その行間から、読者への真摯な想いが少しでも伝われば幸いです。
同業者にも影響を与える分析と人間観察の視点
私のコラムでは、市場分析や投資戦略といった専門的なテーマだけでなく、経営者のリーダーシップや組織文化といった「人」に関わるテーマを取り上げることも少なくありません。
それは、冒頭でも述べたように、「数字の裏には、いつも人がいる」という私の信念に基づいています。
冷静な分析を心がけつつも、その中に時折、人間に対する温かい眼差しや、社会に対する独自の観察眼を織り交ぜることで、読者の方々に新たな気づきや共感を得ていただけることがあるようです。
同業者の方々からも、「佐々木さんの視点は面白い」「ハッとさせられることがある」といった声をいただくことがあり、大変励みになっています。
人生と資本主義を語る時間:ライフスタイルと価値観
仕事から離れた時間も、私にとっては大切な思索の時です。
特に、旧友と楽しむ登山は、心身をリフレッシュさせると同時に、自らの価値観や社会のあり方について深く考える機会を与えてくれます。
登山と旧友との対話から得る内省
山道を一歩一歩踏みしめながら、眼下に広がる景色を眺めていると、日常の喧騒から解放され、思考がクリアになっていくのを感じます。
そして、気心の知れた旧友たちと交わす会話は、多岐にわたります。
経済のこと、社会のこと、そして時には人生そのものについて。
彼らとの対話を通じて、自分自身の考えを深めたり、新たな視点を得たりすることが、私にとっては何よりの刺激であり、学びの場となっています。
「結局、我々は何のために働き、何のために資産を運用しているのだろうか?」
そんな根源的な問いに立ち返ることで、日々の業務に対するモチベーションも新たになります。
投資を「続ける」ために必要な人生観
投資は、短期的な勝ち負けを繰り返すゲームではありません。
むしろ、長い時間をかけて資産を育み、将来に備えるための営みです。
だからこそ、投資を「続ける」ためには、しっかりとした人生観を持つことが大切だと考えています。
- 自分は何を大切にして生きていきたいのか?
- どのような社会を実現したいのか?
- お金を通じて、どのような価値を創造したいのか?
これらの問いに対する自分なりの答えを持つことが、目先の市場の変動に一喜一憂することなく、長期的な視点で投資と向き合い続けるための羅針盤となるのではないでしょうか。
資本主義における「人間らしさ」とは
私たちは資本主義という経済システムの中で生きています。
このシステムは、経済成長や技術革新を促進する一方で、時として過度な競争や格差を生み出す側面も持っています。
そんな中で、私たちが忘れてはならないのは「人間らしさ」とは何か、ということではないでしょうか。
それは、他者への共感であったり、社会全体の持続可能性への配慮であったり、あるいは目先の利益だけにとらわれない倫理観であったりするかもしれません。
投資の世界においても、単にリターンを追求するだけでなく、その投資が社会や環境にどのような影響を与えるのかを考える「ESG投資」のような動きが広がっているのは、まさにそうした「人間らしさ」を求める意識の表れと言えるでしょう。
資本主義の恩恵を享受しつつも、その中でいかに人間性を失わず、より良い社会を築いていくか。
これは、私たち一人ひとりに投げかけられた問いなのかもしれません。
まとめ
年金基金であれ、個人の資産運用であれ、その根底に流れるべきは「信頼」です。
そして、その信頼は、決して数字だけで測れるものではありません。
運用に携わる者の誠実さ、顧客との真摯な対話、そして社会全体への貢献意識。
これらが伴って初めて、真の信頼関係が築かれるのだと、私は30年以上の経験を通じて確信しています。
ファンド運用における信頼は「人を見る力」から始まる。
これは、私が常に心に刻んでいる言葉です。
企業の経営者、従業員、そして何よりも大切な顧客。
一人ひとりの「人」と真摯に向き合い、その想いを理解しようと努めること。
佐々木信一の実践が、皆様にとって、誠実さと対話の重要性を再認識する一助となれば幸いです。
最後に、読者の皆様に問いかけたいと思います。
あなたの投資は、「誰を信じているか」から始まっているでしょうか?
最終更新日 2025年5月20日 by rosseng